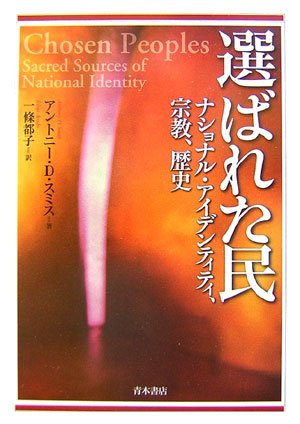ヴィクトリア女王の時代
およそ人とさえ名あれば、富めるも貧しきも、強きも弱きも、人民も政府も、その通義において異なることなし*1
第三編は「国は同等なること」として、第二編において説いた個人の権利を、国家間のレベルで論じたものになる。すなわち、
今のこの義を拡(おしひろ)めて国と国との間柄を論ぜん。
今さらだが、小泉信三による福沢諭吉の評伝*2を読んでいたら気づかされた。福沢の一生はほぼビクトリア女王の治世に重なる。
ヴィクトリア女王の即位は1837年。その2年前に福沢は生まれており、1901年にどちらも亡くなっている。渡英したばかりの夏目金之助が遭遇した行列は、この世界に君臨した女王の葬送の列である。明治34年。
満つれば虧くるの譬えではないが、ビクトリア女王の治世は前後期に分けられ、後期になるとそのほころびが目立ってくるわけだが、それゆえ強引な、大英帝国のインド・清への支配と侵略は「国は同等」でないことを福沢に知らしめたろう。
また、列強諸国が東アジアを植民地化してゆくありさまと、ロシアの南下、合衆国の来航による不平等条約。すべての発端が、パクス・ブリタニカと呼ばれる女王の治世下であったことは、とりわけて英語の学者、思想家であった福沢をして、
自国の富強なるをもって貧弱なる国へ無理を加えんとするは、いわゆる力士が腕の力をもって病人の腕を握り折るに異ならず、国の権義において許すべからざることなり。
と言わしめる。ここで、その「富強」への道を、「学問」による「一身独立」に見出したことはすでに初編に説かれていることだが、福沢はさらに敷衍する。
一身独立して一国独立すること
この章は三つの条に分けられている。それぞれ
第一条 独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず。
第二条 内に居て独立の地位を得ざる者は、外にありて外国人に接するときもまた独立の権義を伸ぶること能わず。
第三条 独立の気力なき者は人に依頼して悪事をなすことあり。
である。
見落としてならないのは、これが書かれた当時、ほとんどの列島住人は〈近代国家〉とか〈民族国家〉とかを知らない、ということである。洋学者や政府枢要の地位にあれば知っていたかもしれないが、それさえ、実地に西欧諸国を視察してそれぞれの理解力に応じて知ったものだ。
よって、外夷への恐怖は、お化けのたぐいの話で、前回記した民衆擾乱が荒唐無稽の流言によって巻き起こったことからも分かるように、無知と言って無知で片づけきれない環境がまず国内にあった。
そして儒教とその影響下に成立した国学イデオロギーは、基本的に〈仁恤〉を治世の徳目においており、為政者は人民に対し、仁徳を垂れることが期待された。中世期以降、それが徳政と呼ばれたことは、どこかに書いたが、多くの民衆騒擾、一揆、打ちこわしが、具体的な要求をもたない自然発生的な騒動であったことからも、為政者は人民の意図を汲むことが期待されし、人民は為政者がそれを汲むことを期待した。
しかし、それでは〈近代国家〉創成はできない。少なくとも西欧列強に侵略されないだけの国家はできない。
第一条 独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず
そこで福沢はここで「独立」とは何かについて述べる。それは〈近代国家〉の重要な条件であるからだ。
独立とは自分にて自分の身を支配し他によりすがる心なきを言う。みずから物事の理非を弁別して処置を誤ることなき者は、他人の智恵によらざる独立なり。
これは儒教の徳目と対蹠的である。すなわち、
民はこれによらしむべしこれを知らしむべからず
の思想からは出てこない。鼓腹撃壌では、国家はその危機に立ち向かえない。
英人は英国をもってわが本国と思い、その本国の土地は他人の土地にあらず、わが国人の土地なれば、本国のためを思うことわが家を思うがごとし。国のためには財を失うのみならず、一命をも抛(なげう)ちて惜しむに足らず。これすなわち報国の大義なり。
福沢はここでだいぶ危ういことを言っている。
そして、歴史に喩えを求め、桶狭間で今川兵が四散したことに対し、普仏戦争で皇帝捕縛のあともパリが抵抗をつづけたことを比較して、封建的主従とネーション・ステート=国民国家との強弱を論ずる。
もちろん、ナショナリズムとその民族自決が、批判的に論ぜられるために人類は二つの世界大戦を必要としたのだからやむを得ない*3が、列強諸国と呼ばれる国々が、ネイション=国民というものから成り立っていることを見抜いた慧眼は見逃してはなるまい。
第二条 内に居て独立の地位を得ざる者は、外にありて外国人に接するときもまた独立の権義を伸ぶること能わず。
もちろん、福沢に、のちの超国家主義者たちが見出すようなネイションに関する〈美学〉はない。愛国心に美しさや素晴らしさを見出してはいない。初編で述べているように、そういう〈美学〉は「さまであがめ貴(とうと)むべきものにあらず」と言っている。「あがめ貴(とうと)むべきもの」への傾倒や、依存を批判しているのである。
よってこの第二条において、
独立の気力ない者は必ず人に依頼す、人に依頼する者は必ず人を恐る、人を恐るる者は必ず人に諛(へつ)うものなり。常に人を恐れ人に諛う者はしだいにこれに慣れ、その面の皮、鉄のごとくなりて、恥ずべきことを恥じず、論ずべきことを論ぜず、人をさえ見ればただ腰を屈するのみ。
「依頼」すること、「恐る」こと、「諛う」こと、そしてそれに「慣れる」ことを否定し、それらからの「独立」を説いている。そのための「学問」ではないか。
第三条 独立の気力なき者は人に依頼して悪事をなすことあり。
先に福沢の論の危うさと書いたが、洋学者でありながら西洋崇拝に陥らない思考は、その徹底した相対主義によって支えられている。当時の日本がおかれた環境、世界の情勢のなかで、よりマシな選択を重ねて書かれている。今川兵とフランス人を比較するのも、彼此の善悪を言っているのではなく、あくまで強弱を相対的な観点から見ている。
よって、この第三条では、
国民に独立の気力いよいよ少なければ、国を売るの禍もまたしたがってますます大なるべし。すなわちこの条のはじめに言える、人に依頼して悪事をなすこととはこのことなり。
とたとえば「外国人雑居」などで「その名目を借りて奸(かん)を働く者」の害を指摘しているものだが、「外国人」が悪いのではなく、「その名目を借り」る者が悪いという論旨になる。それは「独立」ではないからだ。もちろん、これは道徳的な善悪ではない。その「依頼」が「国を売る」ことによる「禍」の大きさ、つまり大小を言っている。
日本語の〈売国奴〉に含まれる感情的な罵言としての語感はここにはない。
パクス・ブリタニカの時代
福沢はオランダから大英帝国にヘゲモニーがうつった、その全盛期と世界に住んでいた。当時、どうにもならないほどの小国であった日本が生き残るためには、〈美学〉や絶対主義に陥ることは許されなかった。
インドや清が抵抗したように抵抗すれば滅ぶしかないし、といってその文明をなし崩しに受け入れればそれはもはや日本ではない。
『学問のすゝめ』において称揚された「実学」は、〈虚学〉=〈美学〉に対置されるものだ。相対主義と絶対主義の違いである。絶対主義が世界の向こうにあるべき姿を見出すのに対し、福沢の相対主義は、あるがままの世界を見る。あるがままの、その世界というゲームのルールを認識させる。前者がゲームのルールに文句をつけることを専らとするなら、福沢はとにもかくにもルールを覚えることを説く。福沢にとって一身一命を賭けて学んだ洋学すら、ここにおいては「実学」、一個の道具に過ぎない。
しかし、そこでうまく立ち回ればいいわけではない。それだけでは「国を売る」ことをも厭わない輩を生むからだ。
よってその「独立」とは、個人や国家、それから列強の作ったルールからの「独立」をもさしている。彼此を比べて相対的にあらゆるものから「独立」してゆくなら、それは当然の帰結である。
今の世に生まれいやしくも愛国の意あらん者は、官私を問わずまず自己の独立を謀(はか)り、余力あらば他人の独立を助け成すべし。父兄は子弟に独立を教え、教師は生徒に独立を勧め、士農工商ともに独立して国を守らざるべからず。概してこれを言えば、人を束縛してひとり心配を求むより、人を放ちてともに苦楽を与(とも)にするに若(し)かざるなり。
第三編を、福沢はこう結ぶ。余計ごとかもしれないが、ここの「愛国」はナショナリズムを意味していない。繰りかえすが、彼此を比べて相対的にあらゆるものから「独立」してゆくなら、その陥穽からも「独立」できるからだ。強いていうなら、仏法にいう方便である。
もちろん、日清戦争だけを見届けて亡くなった福沢諭吉にとって、その先のことはその先の日本人の仕事であったろう。それはヴィクトリア女王が、ヨーロッパ中にいた自分の子や孫同士が、互いに殺しあう、第一次大戦を見ずに崩じたことに、似ているのかもしれない。
いつでも平和は、生きている人間の責任である。