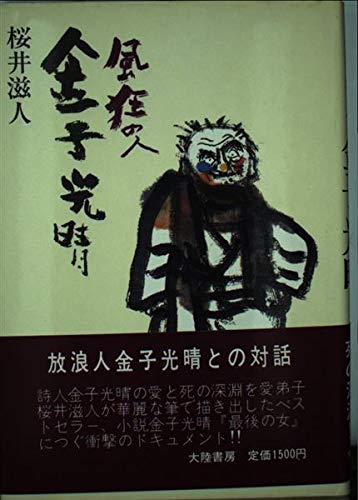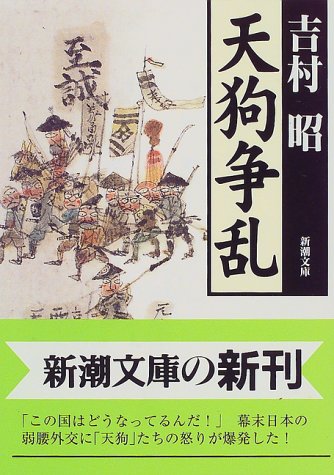前回の『鉛筆紀聞』でさらっと流して書いたが、
dokusyonohito.hatenablog.com
【国内法】
商人が刀剣や鉄砲を所持することはあるのか。
殺人窃盗等の犯罪に関する法律。*パリ郊外において無届の銃使用の禁止のこと。
原文*1は以下のようになる。
「私に刀剣鉄砲を携帯することを得たるや」
並びに
「我在国の日、官へ告げずして獣狩に出、邏官我を執(とら)へて償銀(=罰金)三十元を取れり。是は仏国「パリス(パリ)」」城外の近郊に獣猟を許す地あり。然れども平日、民人婦女、野果を採る為に其中に入て縦行するを許す故に、官人の其内に狩せんと欲するもの、預(あらか)じめ日を期して管に告げざれば、官より民を禁じて其日其内に濫入(=みだりに入る)せしめず。故に、人を誤銃するの災なし。今我其禁を知りながら犯せり。故に銀を出して其罪を償(つぐな)へり。」
※『明治文學全集4』筑摩書房『鉛筆紀聞』より引用
これは突然言われてもちょっと分からない。無断で「郊外」で「銃」を使ってはいけないというなら尤もなような気もするが、もともと王政フランスが庶民に武器のたぐいを所持させなかったことが背景にある。もちろん栗本鋤雲の興味もそこにあったのであろう。庶民の武器所持と、国内治安の問題である。
狼害の歴史
人類史のなかで、近代史で失われたものの中に、〈狼害〉がある。日本だって、昔話には必ず登場する。ペローやグリムの童話でも同断。狼がいなくては始まらない。
しかし、これはその害が絶えなかったどころか、甚大であったことも意味している。
中世期をとおして慢性化した戦争は、狼の餌を増やした。餌があれば増えるのは道理。屍はもとより家畜、家禽、女性や子供、男も襲われた。
年代記作家ウラル・グラベールによれば、1030年から3年にわたったペストの大流行のときは狼が「非常に増え、攻撃的になった」ともいい、葬りきれないほどの死体を残したペストや飢饉もまたその増加の要因になった。これに加えて、狼由来の狂犬病もまた猛威を振るった。かつては死に至る病であったから……。
類例は本書でみていただくのが良いから引用はしない。一例だけ引くと、1796年、ときはもはや共和制に移行していたが、この年で5351頭、翌年1797年には6487頭の狼が狩られたという。それ以前は言うにや及ぶ。
それどころか、ナポレオン帝政に移行すると、ヨーロッパ全土が戦場になり、被害は倍加したという。
狼はけしてファンタジーの生き物ではなかったことを示している。そしてフランス王政下にあっては、この狼害をむしろ助長する権利、制度があった。
狩猟権
本書によれば、フランスの狩猟権は、ヴァロア朝、シャルル6世(1380-1422)あたりにまで遡るらしい。ようは狩りをする権利なのだが、これは王侯貴族の、特権のひとつに数えられていた。
筆者いつもの大雑把でいうと、フランス史を絶対王政への必然につながる歴史としてみるなら、王と貴族・聖職者との支配強化と権利獲得。この二本のあざなえる縄がフランス史、ということになる。
シャルル6世の治世下において聖職者貴族は狩猟の権利を得るいっぽうで、ルイ11世は王権の独占にしようと試みた。
1516年、フランソワ1世(1494-1547)は「王国の貴族でも特権階級でもない者」に狩猟を禁じ、アンリ4世(1553-1610)は違反を企てた者への罰金、むち打ち刑を定め、初犯者には追放刑、再犯者にはガレー船を漕ぐ漕役刑、それでも密猟を重ねた者には死刑、とした。
その罰、苛酷である。
フランソワ1世の出した禁令は、「森林水資源局」を通して出されたもので、近代的な工業化以前の世界では、資源それ自体が資産であるから、その保護という側面もある。けれども、王侯貴族の狩猟と、平民庶民のそれは意味がことなる。趣味と生活のちがいである。
とうぜん増え続ける鳥獣の害に、シャルル9世は王国すべての農民にむけて、「鹿やイノシシを見かけたら、石を投げたり、叫び声を上げたりして耕作地から追い出す」ことの「許可」を与えた。
なんということだろう。「鹿やイノシシ」は狩猟の対象だから、「傷つけてはいけない」ということらしい。
なお、フランス革命における1789年の第三部会で、地方議会が起草した陳情で多かったのは、この狩猟権の廃止であったというから、それまでは王侯貴族と害獣がもたらす被害に、フランスの農民はなすすべがないまま数百年を過ごしたことになる。
いっぽう、害獣のなかでも狼は別で、王侯貴族の狩猟対象になるでなし、害しかもたらさないということで、狼狩猟官なる職位が存在した。
農作物への被害よりはるかに直接的な被害をもたらしたのが狼だから、これを独占的に駆除する役目を負うたのが狼狩猟官だ。地方からの陳情を受けて、王が命令するかたちで執行されるのだが、その陳情を行った地方の住人は、狩猟の期間、一軒につき一人、無償動員された。不参加は罰金が科せられた。
狩猟の権利を独占的に行使するこの職位は、職権乱用、賄賂の強制、地方地域への寄生を生み、本書のたとえを借りれば、「狼狩猟官を選ぶか、狼を選ぶか」は「コレラを選ぶかペストを選ぶか」と同じようなものだったという。
特権の廃止
これほど被害が出ているにも関わらず、住人自ら駆除にあたらなかったのかと言えば、言わずもがな。庶民に武器を持たせない、その所持を許さない、という統治上の要求であろう。じっさい、フランス革命は、庶民がバスティーユへ武器を確保しにいくところから始まったのだから、存外、杞憂でもなかったとも言える。
1789年、大革命とともに立件議会が、あらゆる狩猟の特権を廃止したことで、フォンテーヌブローやコンピィエーニュの「王の狩り場」には数百人の、多くの農民が入り、狩猟を楽しんだ。
これも、翌年1970年には、農業への支障、田園環境の近郊に障害をきたすというので一定の制限がかかる。
とはいえ、フランス革命以降、許可さえあれば狩猟の権利を誰もが行使できるようになった。
大革命以後
1803年には誰でも税金をおさめれば狩猟が認められる法が定められ、狼狩猟官は幾多の変遷をとげながら、事実上名誉職となる。そのいっぽうで、帝政、共和制、と移ろってゆく政権は奨励金を出し、狼駆除に当たる。
今や誰もが、原則的には、狼を狩ることができるようになり、その駆除は〈順調〉にすすんでゆく。
狼による最後の犠牲者は、1918年10月、オート=ヴィエンヌ県のシャリュで殺されたひとりの老婆。そして1986年、記録上では最後となる狼がアリエージュ県で殺された。
「我在国の日、官へ告げずして獣狩に出……」
こうしてみると、栗本鋤雲がカションから聞いた「我在国の日、官へ告げずして獣狩に出……」の一文の意味がわかる。
鋤雲は、民間の武器所持、という当時の幕藩体制における問題意識から問うたのに対し、カションは一言では言い切れない歴史を、ユーモアを交えて語ったわけだ。
とはいえ、鋤雲も、何やら解釈しきれないにも関わらず、カションの言葉のうらに何かを感じ取ったのかもしれない。『鉛筆紀聞』の他のぶぶんと異なって、咀嚼解釈したことではなく、そのまま書いたような書きぶりになっている。
まさかカションだって、極東の果てで、シャルル6世から説明するわけにもゆかなかったろう。
『狼と西洋文明』
本書は訳者によれば、クロード=カトリーヌ・ラガッシュ、ジル・ラガッシュ夫妻の共著。原題どおりなら『フランスの狼』。邦題『狼と西洋文明』。著者はそれぞれ文学者と歴史家なので、言われてみればなるほど、それぞれの視点がはいっている。
おおかまに言うと、
【前半】神話や伝説にみられる狼の意味、象徴、物語における機能を論じる。
【後半】社会史における狼とその狩猟をめぐる歴史を述べる。
というちょっと異色の構成である。もちろん、あたまから順に読んでいくと文学的な見方をもちつつ、歴史的な見方ができ、読了すると歴史から文学をぎゃくに照らし返せるようになっている。
1989年9月10日初版第一刷発行。八坂書店。訳者高橋正男。
「異色」とはこの本にとって、立派な誉め言葉なのである。